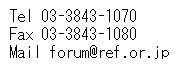Radiation Education Forum
中学生への放射線授業の実践事例
・中学校1年生
・中学校2年生
・中学校3年生
中学校1年生

中学校2年生

中学校3年生





・中学校2年生
・中学校3年生
中学校1年生
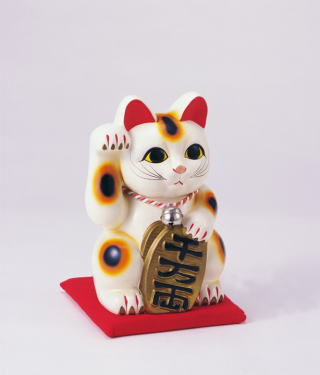 |
事例収集中 |
中学校2年生
| No | 授業名 | 実践学校名 | 実践者氏名 |
| 1 | 明健中学校における放射線教育 動物のからだのつくりと働き ‐放射性物質の半減期及び放射線による人体への影響‐ |
郡山市立 明健中学校 (福島県) |
佐々木 清 町田 峰子 |
| 1.明健中学校における放射線教育 動物のからだのつくりと働き ‐放射性物質の半減期及び放射線による人体への影響‐ (PDF) |
||
| 実践学校名:郡山市立 明健中学校(福島県) | ||
| 実践者氏名:佐々木 清、町田 峰子 | ||
| 放射性物質の半減期と福島県の各地域で行われている除染活動の効果をモデル実験で確かめ、空間線量率が微減する中で、放射線の人体への影響と免疫力について学び、規則正しい生活習慣による健康管理を日常生活での実践に結び付ける。 | ||
 |
1.周囲で行われている除染作業をモデル実験にて体験させ 、効果を考察させる 2.養護教諭とのTeam Teaching授業により、健康管理につ いて考察するとともに日常での実践を考察させる 3.一人学び→ペア学習→グループ学習→全体学習と練り上 げ、科学的な根拠に基づいた思考過程を培う |
|
| ・放射性物質の半減期から、将来の空間線量率の分布を考察 する ・グラウンドの土壌入れ替えのモデル実験により、除染活動 の効果を考察する ・放射線の人体への影響と、影響を緩和する免疫力の高め方 から、日常生活における健康管理を考察させる |
||
中学校3年生
| No | 授業名 | 実践学校名 | 実践者氏名 |
| 1 | 運動とエネルギー 放射性物質の除染とその効果、今後の課題 |
郡山市立 郡山第4中学校 (福島県) |
児玉 剛明 |
| 2 | 平成24年度 湖南小中学校での放射線教育 (中学校3年生、小学校6年生交流授業) 「エネルギーの変換と利用」 |
郡山市立 湖南小中学校 (福島県) |
瀧田 和也 宗像 克典 |
| 3 | 中学校理科 新学習指導要領に沿った 放射線教育の実践報告 〜3時間の授業実践「放射線の性質と利用」〜 |
長南町立 長南中学校 (千葉県) |
小泉 静恵 |
| 4 | 中学校3学年 理科学習指導案 『単元:科学技術と人間(エネルギー資源)』の 学習指導の研究 ‐放射線の性質について‐ |
つがる市立 森田中学校 (青森県) |
乳井 秀樹 |
| 5 | 平成24年度 島根大学教育学部付属中学校における放射線教育 |
島根大学 教育学部 附属中学校 (島根県) |
高橋 里美 |
| 1.運動とエネルギー 放射性物質の除染とその効果、今後の課題 (PDF) | ||
| 実践学校名:郡山市立 郡山第4中学校 (福島県) | ||
| 実践者氏名:児玉 剛明 | ||
| 自然とのかかわりを重視し、自然を探究する力を高めることにより、生徒自身に望ましい自然環境を育てるためにはどうあればよいかを検討させる。 | ||
 |
1.知的好奇心を高める教材や学習活動の工夫 2.生徒一人一人の主体性を活かした研究活動の工夫 3.探究する力をはぐくむ教材・学習活動の工夫 4.知的好奇心の高まりを評価する方法の工夫 |
|
| ・模擬環境での実験による放射線量を下げる除染活動の効果 を考察する ・実験の結果から、除染活動の課題やこれからできることを 考察する |
||
| 2.平成24年度 湖南小中学校での放射線教育 (中学3年生、小学6年生交流授業) 「エネルギーの変換と利用」 (PDF) |
||
| 実践学校名:郡山市立 湖南小中学校 (福島県) | ||
| 実践者氏名:瀧田 和也、宗像 克典 | ||
| 環境の放射線量の測定などの放射線教育を行い、その教育を通じて「自然とのかかわりを重視し、自然を探求する力を高め、より望ましい自然観を育てる授業はどうあればよいか」および「自然に対する知的好奇心を高め、科学的に探究する力を育む学習活動の工夫」についての考察を行った。 | ||
 |
1.思考の履歴が見える学び合い活動の工夫と表現力の育成 2.周囲の放射線を測定することで、データを基に考える力 を養う 3.生徒自らが小学生に教えることを通して、データ処理の 方法について定着を図る 4.関係機関との連携による、授業への助言と支援、実験に 必要な測定器、資料等の準備 |
|
| ・小学生と中学生の合同にて、校舎の放射線を測定し、放 射線が高いところの共通点を考察する ・測定結果を段階的(ペア→グループ→全体)に話し合う ことで、他者の意見を参考に、自己の思考を深める |
||
| 3.中学校理科学習指導要領に沿った放射線教育の実践報告 〜3時間の授業実践「放射線の性質と利用」〜 (PDF) |
||
| 実践学校名:長南町立 長南中学校 (千葉県) | ||
| 実践者氏名:小泉 静恵 | ||
| 「エネルギー資源」全体の授業計画ではなく、「放射線の性質と利用」に絞込み、3時間で最大限どれだけのことを教えるべきかを考察するとともに、すべての中学校で誰にでも新学習指導要領に沿った授業ができるような学習計画案の作成を試みた。 | ||
 |
1.「科学技術の発展」→「エネルギー資源」の順に学習す ると、中学生にとって放射線が単に危険なだけのもので 終わらず、科学技術の発展に欠かせないものであること が理解しやすい 2.周囲環境の放射線量を測定し、放射線が身近にあること を知るとともに、自然放射線の量はごくわずかで、健康 を害するとされる量には全く及ばないことを理解させる 3.多額の費用、特別な設備・道具を一切使用せず、全ての 中学校でできる授業を実践した |
|
| ・X線撮影など、身近な放射線の利用例を導入に、放射線の 性質の利用が、私たちの生活に役立っていることを知る ・測定器を使い周囲環境を測定し、発表しあう ・放射線の遮蔽および距離による減衰の実験を通して、放射 線を正しく怖がる態度を見につけさせる |
||
| 4.中学校第3学年 理科学習指導案 「単元:科学技術と人間(エネルギー資源)」の学習指導の研究 ‐放射線の性質について‐ (PDF) |
||
| 実践学校名:つがる市立 森田中学校 (青森県) | ||
| 実践者氏名:乳井 秀樹 | ||
| 目的意識を持たせた上で、教師の適切な支援の下、放射線の計測実験などに一人ひとりが参加することで、主体的に探究する生徒が育つかを考察する。 また、授業の前後での生徒の意識・知識がどのように変化し、科学的知識を生活に応用できるかを確認する。 |
||
 |
1.霧箱観察により、放射線のイメージを持たせ、「放射線 から身を守る」という課題を解決する目的意識を持たせ た 2.班編成を少人数とすることで、実験や観察に生徒一人ひ とりが直接的に携わることができる時間を多く設定した 3.生徒のつまづきに対応できるよう、放射線の性質などが イメージしやすい演示を取り入れた 4.授業の前後で意識・知識に対するアンケートを実施し、 変化を確認した |
|
| ・霧箱による放射線の飛跡の観察にて、放射線の正しいイメ ージを持たせた ・身近なものから出ている放射線の強度の測定を行うととも に、距離による変化や遮へいによる変化を実験させる ・実験の結果から、課題である「放射線から身を守る」方法 を検討させ、科学的知識を生活に活用する力を身に付けさ せる |
||
| 5.平成24年度 島根大学教育学部付属中学校における放射線教育 (PDF) | ||
| 実践学校名:島根大学教育学部附属中学校 (島根県) | ||
| 実践者氏名:高橋 里美 | ||
| 生徒へのアンケートにより、『疑問に思うこと』、『調べてみたいこと』を抽出し、要望のあった授業を構築した。 実験や観察を通して、放射線の性質についての基礎的な知識を身に付け、放射線の利用とリスクについて理解させる。 |
||
 |
1.アンケートにより生徒の要望がどこにあるのかを確認でき 、生徒の求める知識について授業を構築できた 2.霧箱による自然放射線の観察により、放射線を身近なもの としてとらえさせることができた 3. 放射線の計測には、身近なものを使用することで、生徒の 興味を引き付け、生活環境のいたるところに放射線が存在 することをとらえさえた 4.実験・観察を取り入れながら学習することで、生徒の学習 の定着をはかることができた |
|
| ・目に見えない放射線を、霧箱による放射線の飛跡の観察に て、自然界にも存在することを気づかせる ・放射線測定器による計測にて、単位、測定方法を学習させ るとともに、放射線の『距離の依存性』や『透過能力』な どの性質を学ぶ ・放射線の利用と性質の関連性、放射線の健康への影響と対 策について学ばせる |
||